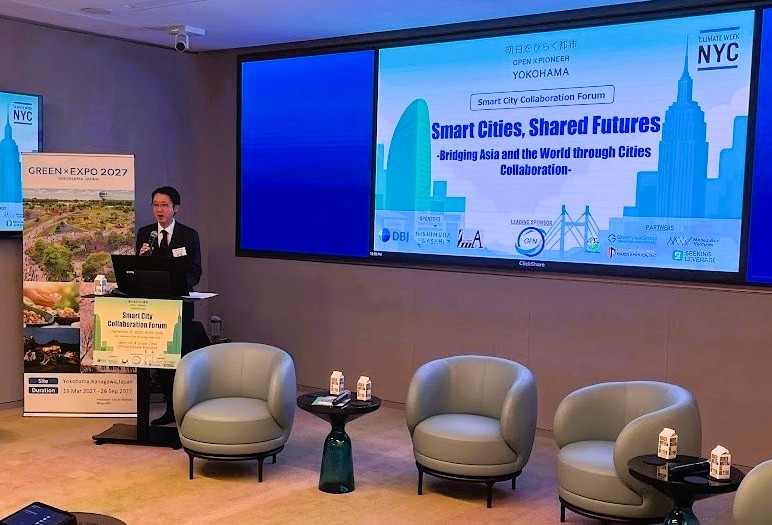横浜市では、グローバル企業の R&Dや技術者の集積といった横浜の強みを生かし、Clean Tech やモビリティをはじめとするテック系分野でのユニコーン・クラスのスタートアップ創出を目指し、グローバルを目指すテック系スタートアップに特化した支援拠点として、2024年11月11日にTECH HUB YOKOHAMA(外部サイト)をオープンしました。
11月18日には、TECH HUB YOKOHAMAにおいて海外スタートアップと日本・横浜企業との協業を促進するため、セミナー・ネットワーキングイベントを開催し、日本企業・海外スタートアップ両方の視点から、海外のスタートアップとの連携におけるヒントや失敗例、海外の最新情報やグローバルな協業をする際のコツなどについてお届けしました。
パネルディスカッション
当日は、バイリンガルのエンジニア出身のベンチャービルダーであり、自身も海外でスタートアップを複数立ち上げた経験を持つ、「ShibuLA Ventures」の二宮 Kevin氏をモデレーターとして、また、パネリストとして、日本の自治体としては横浜市が初めて連携協定を締結したスタートアップ支援機関「Start2 Group」の小田嶋 Alex 太輔氏、米欧をはじめグローバルなビジネスエキスパートである「ITOCHU Europe PLC」の辻良介氏、さらに、スタンフォード大学在学中にモアシス社を起業・その後事業売却をし、現在Anifie社共同創業でもあるシリアルアントレプレナーの岩崎洋平氏をお招きし、様々な観点から海外スタートアップとの連携を促進する上で大変示唆に富む議論がなされました。
言語の違いが一番の障害?
より良いスタートアップを探すために、日本国内に限らず海外を視野に入れることは必須になっているが、日本企業にとって海外スタートアップと連携を図る上で、どのような課題・困難さがあるのであろうか。
海外スタートアップとの連携と聞くと、真っ先に言語の壁が浮かぶと思われるが、興味深いのは、実はそれ以上に文化や価値観の違いから生じるミスコミュニケーションが問題になることが多いということである。例えば、希望的観測をせずはっきりと確認すること、そして相手にはっきりと物事を言われても、面を食らわないなど、いずれも基本的なふるまいであるが、これを欠いてしまったがために後々うまく連携が進まないことがあるという。特に定期的な人事異動を行う日本企業は、熟練した担当者のノウハウやネットワークを引き継ぎづらい構造を抱えており、コミュニケーションは問題になりやすいとの認識が共有された。
なぜ連携するのかをクリアに
ミスコミュニケーションが起こる背景の一つには、「なぜ連携するのか」が組織的にクリアになっていないからだという。KPIになっているPoCの件数が自己目的化してしまい、その後に繋がらないケースや、業界のトレンドがわからないにもかかわらず、技術等に飛びついてしまうケースなどはよくある話として紹介をされた。
また、国内外に関わらず、スタートアップとの連携では、本来自社開発をせずに「スピードを買う」ということを念頭に置く必要があるとの意見もあった。スタートアップ側は資金繰りの問題に常に直面しており、意思決定に時間がかかると協業を進める上で致命的になり、信頼を失う場合もある。これを避けるためには、組織として予め協業目的をクリアし、経営層のコミットメント、人材などのリソースを組織として投入するなど体制を構築することが必要になるという。
確かに、日本企業の意思決定の遅さはよく上げられるが、一方で、一度意思決定がなされると、日本企業のコミットメントは固く、その点が良いイメージとして働く場合もあるという。クライメートテックなどの領域は、そもそも足の長いプロジェクトでもあり、日本企業に信頼を寄せ、連携をしたいという海外スタートアップもいるため、狙っていけるチャンスであることが指摘された。この点は、海外スタートアップとの連携によってどの事業領域をなぜ狙うのか、各企業が戦略をクリアにする際の参考になると思われる。
目に見えにくい部分こそ重要
その後、QAセッションでは、外部コンサルの活用の仕方や、市場サイズ以外にレギュレーションなど多岐にわたる視点で事業領域のアセスメントを行うこと、オープンイノベーションを担う人材育成をどう進めるかなど多岐にわたる質問があり、参加者の関心の高さが伺われた。Kevin氏は、「海外とのオープンイノベーションを進める上では、実は言語や拠点など、ぱっと見えるものよりも、人材やマインドセットなど目に見えにくい部分で苦労するケースが多く、裏の部分の基盤整備をどれほど整えられるかが重要であることが分かった」と、今回の議論をクロージングし、その後、ネットワークで活発な意見交換がなされた。
TECH HUB YOKOHAMAでは、”Tech and Global”を掲げ、今後ユニコーン企業の創出を目指していくが、横浜市米州事務所としても、今回のイベントを含め、北米現地のネットワークを生かし、今後、横浜企業と海外スタートアップとの連携促進に向けてイベント開催等、取り組みを強化していきます。